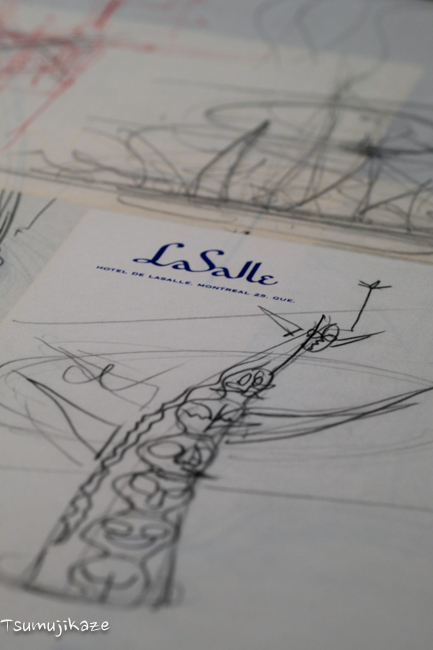さらば人形町 [寫眞歳時記]
4年間勤めた人形町の子会社の代表を退任して古巣の本社に戻ることになった。本社の所在地は神田なので隣町に移動するだけで大した違和感はない。だが、共に働いた仲間たちと慣れ親しんだ町と別れるのには一抹の寂しさがつきまとう。何時でも会えるし行ける距離なのに不思議なものだ。コロナ禍の中を戦い抜いた同志たちに感謝しつつ一旦この地に別れを告げる。
振り返ると人形町界隈の写真を真面目に撮っていないのに気づく。中々、仕事場の近所でカメラ爺いになりきるのに抵抗があったのかもしれない。今度はのんびり徘徊するつもりだ。因みに来月からは完全な窓際族と思われたが、名古屋地区の責任者に任命された。爺いをこき使う素晴らしい親会社に感謝![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif) あの名古屋メシを定期的に食えるだけでも楽しみが増えた。これからも、人も食も景色も「一期一会」を貫きたいと思うのだった。
あの名古屋メシを定期的に食えるだけでも楽しみが増えた。これからも、人も食も景色も「一期一会」を貫きたいと思うのだった。
東京の春を見っけ! [寫眞歳時記]
台東区蔵前近辺を彷徨いていたら、小さな神社に人だかりを見つけた。まだまだ肌寒い日が続く東京だが、気の早い春の使者が控えめに街のあちこちで季節の変わり目を告げているようだ。
蔵前神社の狭い境内では、ミモザが咲き乱れ、早咲きの桜と見事なコントラストを示して、春の訪れを主張していた。
『東京都庭園美術館』開館40周年 [寫眞歳時記]
1933年に竣工した旧朝香宮邸が都立美術館として一般公開されて40周年を迎えた。通常は重要文化財に指定された洋館で国内外の数々の美術品を愛でる非日常を味わせてくれる貴重な場所だ。今回は周年事業として、「開館40周年記念 旧朝香宮邸を読み解く A to Z」と題して旧朝香宮邸自体の魅力に焦点を当てた企画展が開催されている。普段は展示された美術品に目を奪われがちで通り過ぎていた館内の意匠に心が弾む。今会期中のみ写真撮影可能とのことで、あるがままの姿に戻った90年前の邸宅を存分に愉しんできた。
表参道のピカソと岡本太郎 [寫眞歳時記]
幼少の頃から馴染み深い菓子なのだが名前は知らなかった。

1969年の発売以来、超ロングセールスを続ける「シガール」は『ヨックモック』の顔とも言うべき主力商品である。営業先での珈琲のお供に添えられていたりお客様から手土産として頂いたり、自分では買って食べる事は無いのに印象深い不思議なお菓子だ。そんな老舗の洋菓子メーカーが南青山で美術館を運営している事も小生は当然知らなかった。
南青山の「ヨックモックミュージアム」は、「菓子は想像するもの」というメーカーの理念に基づき、自由な発想から生まれるピカソのセラミック作品を中心にコレクションしている美術館だ。建築家・栗田祥弘が5年の歳月をかけて2020年に竣工した。外観・内装共に斬新だがシンプルなデザインに心が洗われる。1階がショップ&カフェで地下と2階の展示室にはピカソの手掛けた陶器がテーマごとに陳列されている。
いつもの癖でコーヒータイム
絵画の大作などは一点も無いが、心落ち着く空間で巨匠ピカソのエッセンスと向き合う事が出来た。休日でも混み合う事なく、快適な時間と空気感を味わえる貴重な場所かもしれない。ケーキを旨いし![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)
此処から歩いて5分ほどで、今度は我が国が誇る天下無双の奇才に会える。
此処から歩いて5分ほどで、今度は我が国が誇る天下無双の奇才に会える。
岡本太郎が42年間住まい作品を作り続けた自宅兼アトリエが、彼が逝去した2年後の1998年に『岡本太郎記念館』として公開された。建物は坂倉準三の設計によるもので、まさに戦後芸術界の巨匠と奇才のコラボとも云うべき独特のフォルムに目を奪われる。
未だに盛り上がらない大阪万博を来年に控え、前回開催の70年万博を振り返る風潮が強くなっているようだ。そのアジア初の国際博覧会のシンボルになったのが、岡本太郎の手による「太陽の塔」だ。今、静かなTAROブームが起きており、館内は子供連れを含めて結構混雑していた。
未だに盛り上がらない大阪万博を来年に控え、前回開催の70年万博を振り返る風潮が強くなっているようだ。そのアジア初の国際博覧会のシンボルになったのが、岡本太郎の手による「太陽の塔」だ。今、静かなTAROブームが起きており、館内は子供連れを含めて結構混雑していた。
元自宅兼アトリエである為に広い展示スペースではないが、その分TAROイズムが凝縮されており、稀代の芸術家の息吹まで感じられる美術館だ。彼は青年期にパリでピカソの作品に衝撃を受け抽象画の道に進んだと云われる。続けざまに二人の作品を目の当たりにすると、人間の自由な発想が無限であることを痛感し、常人では辿り着けない境地を同時に垣間見てしまった思いだ。
さらにもう少し歩けば「根津美術館」に行けるが、気分は既にアバンギャルドなので、表参道駅から一駅の渋谷駅に出ることにする。
井の頭線渋谷駅に向かうコンコースには壮大な壁画が存在する。雑踏の中から立ち止まって見返す人などほとんどいない色鮮やかな抽象画なのだが、これが「太陽の塔」と対を成す岡本太郎の傑作と呼ばれる「明日の神話」である。1968年頃にメキシコのホテルの壁画として製作されたが、ホテルの倒産により長らく行方不明になっていた曰く付きの作品なのだ。2003年に偶然発見されて帰国、敏子未亡人が中心となり修復が施されて2008年から現在の場所に設置された。昨秋から再度の大改修がスタートし、現在第一工程が終了された直後だ。今後数年をかけて全面的な修復を行うらしい。
画面中央付近で原爆が炸裂し、右画面にかけてその災禍に苦しむ人類の姿が描かれている。一方、左画面には悲劇を乗り越え、生を謳歌する人々が垣間見える。大きな過ちを経てもなお未来に向けて踏み出す人間の愚かさと逞しさを TAROは訴えたのだろうか?